ロードバランサとは
ロードバランサとは、サーバの負荷分散を行いつつ、冗長化を実現するアプライアンス機器です。http(s)サーバを負荷分散するイメージが強いですが、DNSやIMAP、RDP(リモートデスクトップ)等の様々なプロトコルに対応しているものが多いです。また、サーバの信頼性を上げる機器でもありますので、大抵、このロードバランサ自体もVRRPのような自動切り替わり可能な冗長化機能を持っています。
仕組みとしては、ロードバランサ上の1つのVIP(Virtual IP: 仮想IPアドレス)に、負荷分散させたいサーバ群の実IPアドレスたちを紐付けます。そして、VIPへのアクセスがあった際に、設定された負荷分散ルール(負荷分散方式、および、パーシステンス方式)を元に、実IPアドレスに変換させます。この動作は、実質リバースプロキシと同じ動作になるため、ロードバランサをリバースプロキシとして構成することも稀にあります。(Windowsサーバを直接DMZに晒したくない時等)
補足ですが、L4 レベル (TCP/UDP 送信元宛先ポート) の情報を使ってNextHopを決める機器を L4 スイッチ、http や RDP 等のアプリケーションの中身を見て NextHop を決める機器を L7 スイッチと呼びます。なのでロードバランサのことを L7 スイッチと呼ぶこともあります。
製品の種類
製品としては Citrix の Netscaler、F5 の BIG-IP 等が有名です。安価なものだと、セイコーソリューションズの Netwiser が挙がります。
AWS の ELB (Elastic Load Balancer) も仕組みとしては大枠は同じですので、本記事がある程度参考になるかと思います。
また、Windows サーバの場合はハードウェアを追加購入しなくても、NLB (Network Load Balancing) という機能が無料で使えますが、こちらは仕組みがだいぶ異なります。(紛らわしいことに AWS の ELB の種類にも NLB : Network Load Balancer が存在しますが、全くの別物です。)
負荷分散方式
負荷分散方式の代表的な例を以下に挙げます。
- ラウンドロビン・・・最初に来た通信を Web サーバ#1へ、次に来た通信を Web サーバ#2へ、と順番に割り当てていく
- 最小レスポンス時間・・・死活監視を行った際のレスポンス時間が一番短いサーバを使う
- 最小コネクション数・・・一番接続数の少ないサーバを使う
- 最小利用帯域・・・一番トラフィック流量の少ないサーバを使う
パーシステンス方式
ロードバランサは通信を割り振りますが、サーバ間の同期までは面倒を見てくれません。また、サーバ側も『1 つの Web サーバでのセッション情報を他のサーバに同期する』ということは出来ません。なので、ロードバランサ側で、『あるユーザが色々な Web サーバを行ったり来たりせず、1 台の Web サーバを見続けさせる機能』を用意しています。それが、パーシステンス機能です。
パーシステンス方式の代表的な例を以下に示します。
- クッキー・・・http のクッキー情報をロードバランサが挿入し、ユーザを識別する。同じクッキを持つ通信は必ず同じ Web サーバを使わせる
- 資格情報・・・RDP のユーザ ID 情報を識別する。同じユーザ情報わ持つ通信は必ず同じ Terminal Server (TS) を使わせる
- 送信元 IP・・・同一 IP の通信を同一ユーザと見なす。同じ送信元 IP の通信は必ず同じサーバを使わせる
ロードバランサでの https 通信対応 (TLS/SSL暗号化および復号化)
https 等の暗号化された通信でも、この L7 のスイッチングを実現したい、という需要が多くあります。
これを実現するためには、暗号化されている https 通信等を復号化させて http の中身を見る必要があります。
つまり、TLS 終端を『クライアント⇔サーバ間』ではなく『クライアント⇔負荷分散装置間』にします。
その関係で、ロードバランサには SSL アクセラレータ(通常 CPU に処理させる TLS 暗号化・復号化を、専用 ASIC によりハードウェア処理させる)機能を持っていることが多いです。
実装としては、本来サーバに配置すべきデジタル証明書および秘密鍵をロードバランサに配置し、PC とロードバランサ間は、そのデジタル証明書および秘密鍵を使って https 通信を行い、ロードバランサはそれを http に復号化し、http のクッキー情報を挿入・閲覧し、クッキーに応じた Web サーバへ http 通信を送ります。
ロードバランサと Web サーバの間はセキュリティが下がりますが、2 つの機器の間が距離的に近くにあり、その間であれば盗聴(パケットキャプチャ)はされない、という前提であれば問題はありません。
ですので、Web サーバにはデジタル証明書を配置する必要はありません。ただ、有っても害は無いので、デジタル証明書のライセンス的に問題ないのであれば(昔は配置する機器1台につき 1 ライセンスでしたが、最近は同じ証明書であれば OK のものも多い)配置しておいたほうが万が一の対応としてロードバランサを経由させず直接 Web サーバに https 通信させることができるので良いかもしれません。
ロードバランサの通信イメージ
ロードバランサの通信イメージを以下に示します。
ロードバランサとDNSラウンドロビンの決定的な違い 〜負荷分散と冗長化はイコールではない〜
冒頭で、『負荷分散と冗長化を実現する』と書きました。もしかしたら「負荷分散出来ているなら、冗長化は自然と出来ているでしょ」と思ったかもしれませんが、厳密には異なります。
その一番分かり易い例は、DNS ラウンドロビンです。これは負荷分散は出来ますが、冗長化は出来ません。DNS ラウンドロビンでは、ロードバランサと違い、死活監視を行わないためです。
ロードバランサの構成パターン
ロードバランサの構成パターンは大きく分けて2つあります。
1つが Destination-NAT (DstNAT) 構成、もう1つが Source & Destination NAT (Src&DstNAT) 構成です。
DstNAT 構成
VIP をサーバの実 IP に DstNAT 変換します。
この構成のメリットは、送信元 IP が変換されないため、サーバ側で送信元 IP のログが残せることです。
一方、デメリットは、戻りの通信がロードバランサを経由するようにしっかりと設計する必要がある点です。
構成例として一番素直なのは『2アーム構成』と呼ばれ(インライン方式とも呼ばれます)、ロードバランサの背後にサーバ専用のセグメントを作ることです。ロードバランサから 2 本の足(アームだから腕?!)が出ます。
また、ちょっとトリッキーな構成にはなりますが、Linux サーバであれば、IPROUTE2 による PBRを行うことで、ロードバランスするプロトコルだけ NextHop をロードバランサに向ける、というやり方もあります。この構成は 1 アーム構成と呼ばれます。
また、この IPROUTE2 を使った実装ではさらにトリッキーな構成として、ロードバランサの VIP でも Web サーバの実 IP でも両方 https 通信できる状態にすることができます。
これにより、高価なロードバランサの購入を 1 台に抑えつつ、ロードバランサ障害時には DNS のレコード変更(もしくはクライアントの hosts ファイル追記)のみの簡易な手動切り替えで暫定対応ができる構成を組めます。
さらに発展させ、証明書のエイリアス(サブジェクトの別名、サブジェクト代替名)を使えば、ロードバランサ障害時はクライアント側で URL を変えるだけで対応できます。
Src&DstNAT構成
VIP から実 IP に Destination NAT するタイミングで、一緒に Source NAT すれば、戻りの通信は必ずロードバランサ経由になるので、ネットワークの考慮は不要になります。
ただし、デメリットとしてサーバ側から見たらアクセス元の IP が全て同じになってしまいます。
ですが Web サーバへのアクセスログについては、http の X-Forwarded-For (XFF) 属性や、Proxy protocol 使うことでこの問題は解決できます。
ロードバランサにて http の中身に X-Forwarded-For の属性や Proxy protocol の情報を追加し、その属性値として Source NAT 変換前のIPアドレス(つまりクライアントの IP アドレス)を記載します。
Web サーバ側では、アクセスログの送信元 IP として「X-Forwarded-For 属性がある場合はこちらをログに残す」という設定を入れておきます。構成例を下記に示します。
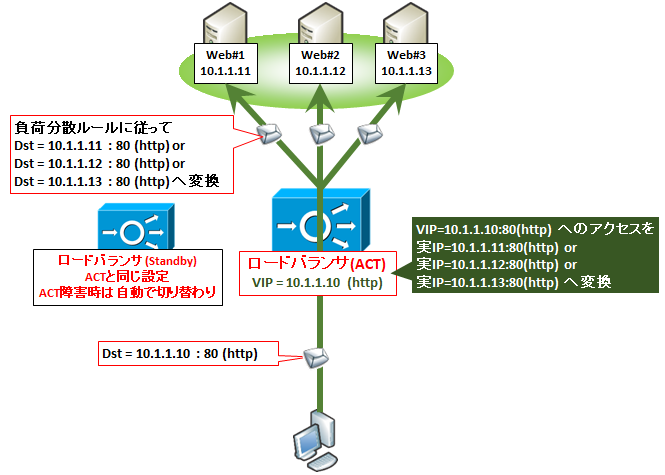
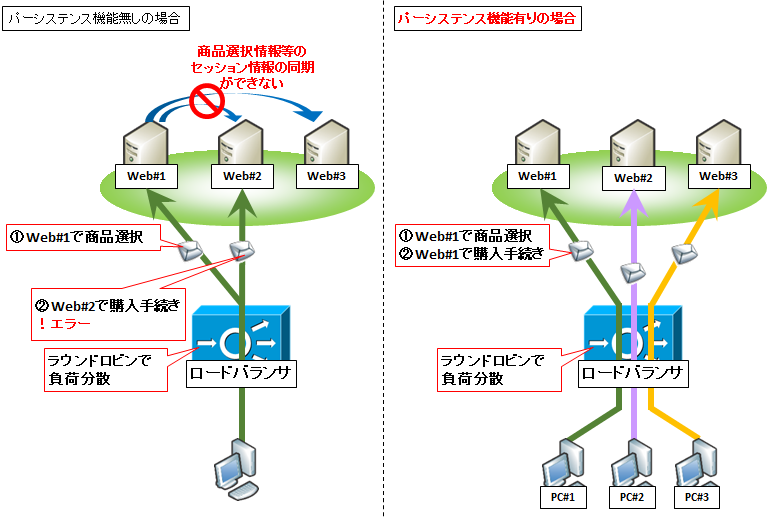
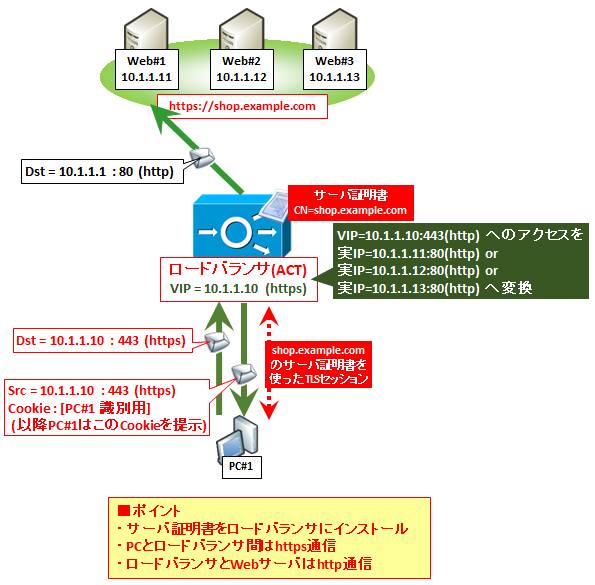
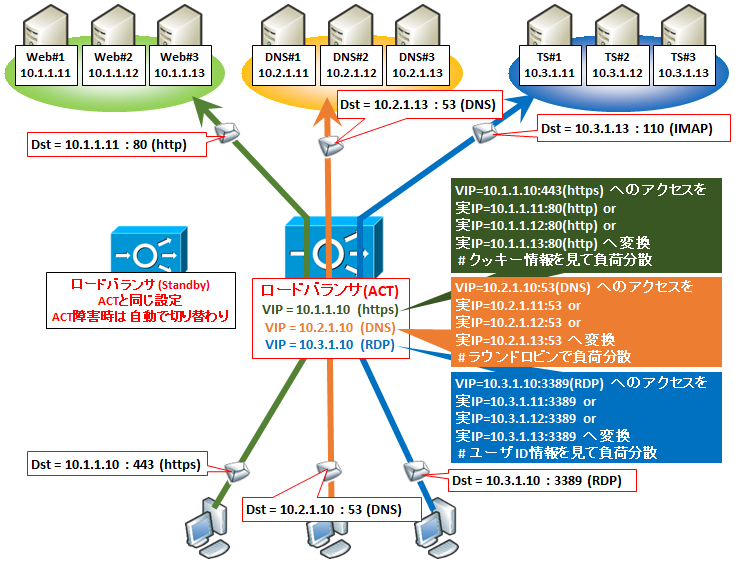



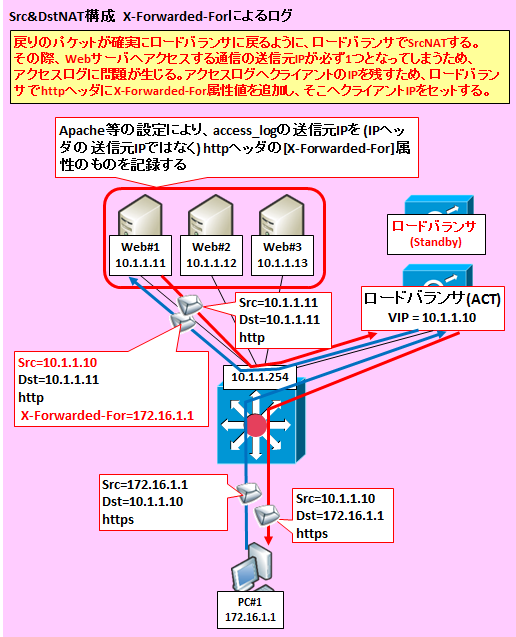
コメント